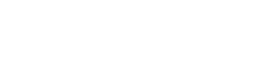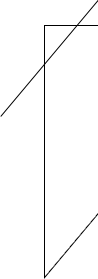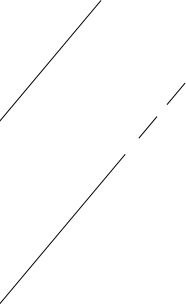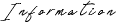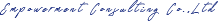そのペナルティが持つ意味は?
サッカーを観ていると、
意図的にファウルで止めたんだろうなぁというシーンを目にします。

素人の僕は知らなかったのですが、SPA(スパ)という用語があるそうです。
これは「Stop a Promising Attack」の略語で、
大きなチャンスとなる攻撃の阻止、を指すそうです。
相手のチャンスをファウルで止める行為は、
主審がSPAと判定するとイエローカードが提示されます。
スポーツにおける意図的なファウルの是非は置いておいて、
何かしらのペナルティを想定、覚悟してのプレーは難しそうですね。。。
このペナルティ、マネジメントや組織のルールで使用されるケースもあると思いますが、
ちょっと気をつけないといけないぞ、という事例がありましたので紹介します。
書籍『その問題、経済学で解決できます』(著:ウリ・ニーズィ-/ジョン・A・リスト)にて紹介されている、
ある幼稚園のお迎えに関する話です。

以下、同書より引用抜粋、加筆修正
イスラエルのある保育園では、親御さんのお迎えの遅刻に悩まされていた。
そこである日、子供を迎えに来るのが10分以上遅れた親御さんからは、
10シュケル(約3ドル)の罰金を頂きます、と発表した。
さて、この保育園がつくったインセンティブはうまく働いただろうか。
実は、全然うまく働かなかった。
そこで、20週間にわたり、イスラエルの保育園10ヶ所で、
迎えに来るのが遅れた親御さんに対する少額の罰金が及ぼす影響を計測した。
最初、罰金がないとどうなのかを測り、それから保育園6ヶ所で、
10分以上遅れた親御さんに一律3ドルの罰金を科す制度を導入した。
結果、遅れてくる親御さんは大幅に増えた。
いったん罰金を導入した保育園では、罰金を科すのをやめても、
遅れてくる親御さんの数は増えたままだった。
どうなっているのだろう?
これは、罰金を科すことで、迎えに来るのに遅れることの意味を変えてしまったのだ。
罰金が導入される前、親御さんたちは単純な暗黙の合意の下で働いていた。
ただ罰金が導入されると、親御さんたちと合意の中身が変わった。
遅刻の価格をはっきりと示したことで、
遅れるのはもう、暗黙の合意に反するものではなくなった。
先生たちの残業は、駐車場とかスニッカーズと変わらないありふれた商品になった。
市場に基づくインセンティブが不完全な契約を補って完全なものにした。
遅れるのがどれだけ悪いことか、今や誰もが正確に理解した。
罰金を科すのは罪の意識に訴えるよりもずっと効果が薄いのを、保育園は思い知った。
・・・どうでしょうか?
お迎えに時間遅れることは、
どの親御さんも悪いこと(サービスの範囲外)と認識していた為、罪の意識がありました。
しかし、それに明確に罰金(ペナルティ)が設定されたことで、
「その金額を支払えば問題ない」というように、
罪の意識の発生しない単なる対価となった、ということでしょうか。
何かしらのペナルティを科している組織は、ドキッとしたのではないでしょうか。
ペナルティが必ず失敗するというわけでは、決してありません。
ポイントは、その行為の価値が明確に意味づけされる、ということです。
その意味(価値)をどう判断されるか?
インセンティブ、ペナルティは、その活かしどころをしっかりと見極めましょう。
そして理想は、それ(インセンティブ・ペナルティ)に頼らない組織です。
あるべき組織の動きが、当たり前になるように。
さて、どんな”当たり前”を創りましょうか?
追記)
まぁ、その当たり前を如何に創っていくか?が難しいのですが・・・・
その際は、是非下記もご参考下さい。