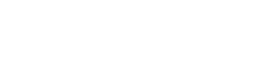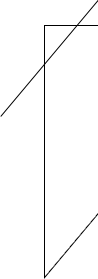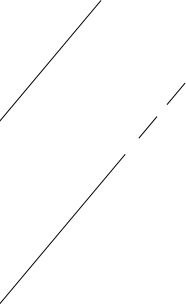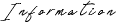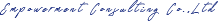その計画をプレモーテムで考える
以前のある投稿にて、
達成された未来から逆算して戦略を練るアプローチ・思考法を紹介しました。
※詳しくは下記のタイトルか画像をクリック
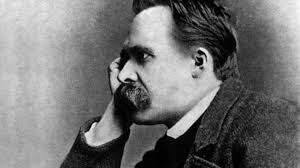
「○ヶ月後、計画が見事達成しました!さて、その要因は・・・・」
と思考していくことで、現状に過度に捉われず、柔軟な発想が可能になります。
これをワークで実施してみると、なかなか好評です。
そりゃそうですよね。
うまくいった(達成された)ことを想像することは、単純に気持ちが良いモノです。
ただ、気持ちは良くないかもしれませんが逆のアプローチも効果的です。
プレモーテムという思考法をご存知でしょうか。
元々は医学界の用語だそうです。
モーテム(mortem)は、ラテン語の単語で、少し物騒ですが「死」を意味します。
それのプレ(pre)なので”死ぬ前”ということです。
つまり、死(失敗)の事前。
「○ヶ月後、計画は残念ながら失敗しました!さて、その要因は・・・・」
と思考するアプローチを指します。
以下、書籍『決断の法則』(著:ゲーリー・クライン)より引用抜粋、加筆修正
計画実行後に何が起きるかを予期する方法を「プレモーテム方策」と呼んでいる。
この考え方は、ある仮説に基づいている。
それは、人が何かを解釈する場合、
特に経験の浅い分野では、自分の判断に対して自信過剰になるということだ。
計画を立案する場合も、自分の計画に欠点は無いと信じたがっているのだ。
そこで、私たちはある練習問題をつくった。
これは、自らの計画を正当化し、欠点を無視する態度を回避するものだ。
つまり、彼ら自身に、積極的に自らの計画の欠点を探させるのである。
まず、計画立案者たちに、
彼らの立案した計画が数ヶ月後に実行された結果を想像するように依頼する。
そして、その計画は失敗に終わったと仮定する。
つまり、失敗したという事実だけが分かっているとする。
そこで、失敗した原因と考えた内容を説明しなければならない。
説明できるような原因を探さなければならない。
すなわち、ここで自分の計画への執着を捨てさせるのである。
そして、失敗の原因を明確にすることで、自らの創造性を発揮させようとしているのだ。
このプレモーテム方策の効果によって、最初の計画への執着は低くなる。
また、これを新プロジェクトのキックオフミーティングの議題に含めて、
問題の明確化に役立たせることができる。
どうでしょうか?
気が進まないかもしれませんが、
計画(プロジェクト)が失敗してしまった!と仮定します。
そこから発想することで、
じゃあ、失敗の理由や、原因は?
では、それを防ぐための対策は?
そもそも、この計画では・・・?
と対策の立案と計画の修正が可能になるということです。
個人でも可能ですが、組織で実施することもお勧めです。
我々がコミットするべきは、結果です。
その為のプロセス・計画に固執・執着する必要はなく、柔軟に対応したいのです。
「出る前に負けること考えるバカいるかよ!」

とは、アントニオ猪木氏の言葉です。
戦う直前や最中(計画がスタートしてから)は、
勝利に向かって計画の実行に集中するべきですが、
その計画の立案時には、負けない為にも負けたことを考えてみましょう。
気が進みませんか?
失敗した時のことを考えて対策を打ったことによって、
うまくいったという未来を想像して、
そこから逆算(バックキャスト)して・・・?
・・・よくわからなくなってきました。
良薬口に苦し、実施をお薦めします。
追記)
成功したと仮定しての思考、失敗したと仮定しての思考、
どちらもバックキャストという未来視点での想像力が求められます。
タイムマシンでもあれば、トランクスくらいハッキリ言えるんですが・・・

出典:『ドラゴンボール』 420話 未来に平和を
まぁ、会議でこう言われても揉めますけどw