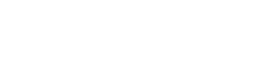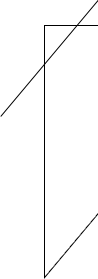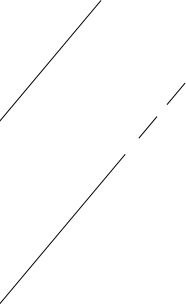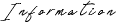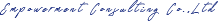学習者同士のつながりがカギ
皆さん、最近どのようなワークショップに参加されましたか?

ワークショップとは、
参加者の主体性を重視した体験型の講座、グループ学習、研究集会などを指し、
参加者同士が積極的に交流しながら学ぶ場を表す言葉として広く使われています。
ですが、その名の通り本来は「作業場」「仕事場」を意味しますので、
日々の仕事をする環境そのものが、交流しながら学ぶ場ということなのかもしれません。
皆さんの職場は、しっかりと交流しながらr学べる場にもなっていますでしょうか?
成長は環境に依存します。
教える側、教わる側の関係性をこれまでも色々と考えてきましたが、
ある興味深い視点がありましたので、ご紹介します。
書籍『アオアシに学ぶ「答えを教えない」教え方』(著:仲山進也)にて記載の
”1対n対nの実践コミュニティ”という考え方です。
※ちなみに「アオアシ」とは、このブログでも度々引用しているサッカー漫画で、
めちゃめちゃ面白い上に、特に組織論や育成に関して学びがありオススメです
以下、書籍『アオアシに学ぶ「答えを教えない」教え方』より引用抜粋、一部加筆修正
1対n対nとは、発信者と受信者が双方向であるのに加えて、
受信者(学習者)同士もつながって学び合いのコミュニケーションをしているカタチを指します。
特に「n対n」がつながっているところが重要です。
では、指導者と学習者が「1対n対n」型につながると何がよいのでしょうか。
学習者同士の横のつながりがあると、他の学習者からいろいろなことが学べます。
自分よりレベルの高い学習者からの学びが役立つのはもちろんなのですが、
「同レベルの仲間との学び合い」がとても重要です。
その中から一人でも切磋琢磨できる関係の仲間ができると、自分が壁にぶち当たったり、
意欲が下がったりした時に「あいつががんばっているなら自分もやらなければ」と
踏ん張りやすくなるからです。(レベルが違う人とは、そういう関係にはなりにくい)
また、メンバーが多様で異なる強みや背景を持っているほど、
化学反応によって大きな共創価値が生まれる可能性が高まります。
さらに、学習者の人数が多くなった場合も、指導者がキャパオーバーになることなく、
横のつながりによって全体の学びの総量を増やしていくことができます。
・・・どうでしょうか?
皆さんの組織は、学習者同士のつながりがありますでしょうか?
指導者は学習者に対して、懇切丁寧に指導したいのですが、
それが過度な依存関係とならないように注意するべきだ、とのことです。
それを補完するのが学習者同士のつながりであり、
互いに学び合うことで新たな価値、気づきを期待できるのです。
成長は環境に依存します。
よりよく学び、成長するためには、
学習者同士がつながる「1対n対n」がひとつのキーになりそうです。
つながっていきましょう。
つなげていきましょう。
追記)
学習者同士がつながる(つなげる)為の一つのアプローチが、
教わるを教えるに転換することです。
僕は、このフェースが決定的に重要だと思っています。
詳しくは、下記をご参考ください(タイトルか画像をクリック)