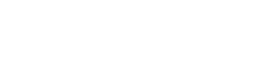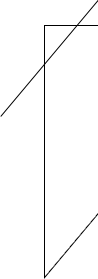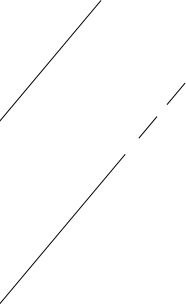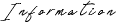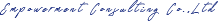我以外皆我師を実践するカラス
”人は教えることによって、最もよく学ぶ”
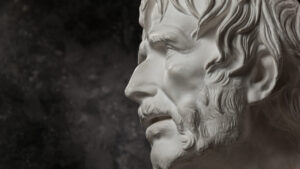
古代ローマの哲学者、セネカの言葉だそうです。
教える側になる(教える機会を得る)ことが成長に繋がる、と
度々このブログでもお伝えしておりますので、この法則は共有・共感頂いているかと思います。
詳しくは、下記もご参考下さい(タイトルか画像をクリック)
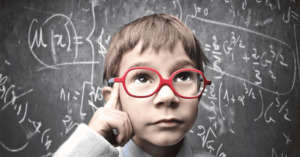
組織の成長を推進していく上では、若手や経験の浅いメンバーにこそ、
誰かに教える機会を提供する必要があります。
そう考えると、ひとつ重要な視点がありました。
若手が教える側ということは・・・
ベテラン(管理職)の皆さん、教わる準備ができていますでしょうか?
そんなことを考えていると、手本になる動物がいました。
カレドニアガラスをご存知でしょうか。
カラスは鳥類の中でも賢いとされているのですが、
このカレドニアガラスは、その中でも別格だそうです。
なんと、道具を自作して使用することができるそうです。

樹木の裂け目や穴の奥深くに隠れている幼虫を好むのですが、
クチバシではなかなか届きません。。。
そこで、適当な葉や枝をクチバシを使って上手に棒状に加工し、
それを利用して獲物を引っ掛けていくのです。
ここまでなら、賢いカラスがいたもんだ、という感じなのですが、
更に驚くべき習性があります。
以下、書籍『「動物行動学入門」 動物のひみつ』(アシュリー・ウォード著)より引用・加筆修正
カレドニアガラスは、動物の知性に関する常識を塗り替えた存在である。
カレドニアガラスたちが残した道具を収集し、詳しく調べると、
この驚くべき鳥が長い時間をかけてどのようにお互いから学び、
幼虫を捕まえる道具をどのように進歩させていったかがわかる。
どうやら工学的知識が狭い地域内の鳥の間、特に親族の間で交換されているらしい。
ただ道具を使うだけでなく、道具使用に関する革新、改良を世代から世代へと引き継ぐ。
所謂、累積的文化進化が見られる唯一の非哺乳類ということだ。
カレドニアガラスから私たち人間が学べることもある。
人間を含め、大半の動物の場合、
知識は年長者から年少者へ、先生から生徒への一方通行で伝えられる。
年少者から年長者へと何かが教えられることはまずない。
ところが、カレドニアガラスは、解決すべき新たな問題に直面した場合には、
ただ一方的に年長者が年少者に教えるだけでなく、年長の鳥が若い鳥に学ぶこともよくある。
・・・カラスがここまで賢いと、
ちょっと恐怖を憶えるのは僕だけでしょうか。。。
使用している道具の変遷を辿ると、それが世代で改良・進化しているというのです。
そして、現場で問題に直面し、そこで改良を加えた場合、
そのノウハウが時には若い鳥から年長の鳥にも伝えられ、広まっていくそうです。
イノベーションには、現場の生の情報と柔軟な思考が欠かせません。
ベテランこそ、それをしっかりと”教わる”姿勢が必要なのではないでしょうか。
我以外皆我師(われいがいみなわがし)※を
実践しているカレドニアガラスを見習わなければなりません。
※吉川英治氏の座右の銘
教え方が色々と難しいと言われる昨今、
逆に若手からうまく教わることができている組織は、強いのかも知れません。
当然、教える側の成長も見込めますので、まさに、一石二”鳥”です。
追記)
要は皆が教える側であり、教わる側であることが重要ですので、
若手やベテランである、という区別は別にいらないのです。
ですが、ついついできるようになってしまう(ベテランになる)と、
教わる姿勢が疎かになってしまうこともありますよね・・・、反省。
そんな時は、下記も参考にして下さい(タイトルか画像をクリック)