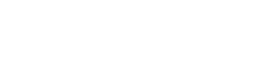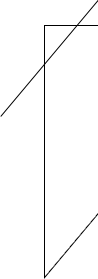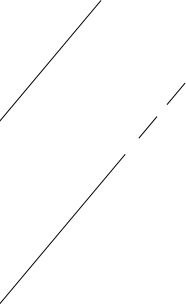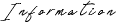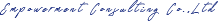水辺の馬とコーチアビリティ
”馬を水辺に連れていけても、水を飲ませることはできない”

西洋の諺ですが、ビジネスシーンでも屢々引用されるので、
聞き覚えのある方も多いと思います。
意味合いとしては、
環境や機会を与えることはできても、
受け手が自ら行動しない限り成果は出ないよね、という感じです。
指導育成のシーンを思い浮かべてください。
熱心に指導しているつもりだが、どこか主体性が感じられない。
水辺には一緒にいるものの・・・という状態でしょうか。
共感される方も多いのかもしれません。
これは、コーチアビリティという理論で説明できる部分があります。
書籍『叱らない時代の指導術』(著:島沢優子)にて紹介されています。
同書によると、
指導者の説明が理解できない際に「ここがわかりません」と、
正直に自分の考えを表現し、
指導者と建設的な対話ができる選手の能力を
「コーチアビリティ」と呼ぶそうです。
時には、「もっとこうした方が・・・」と意見したり、
「それって、この考え方であっていますか?」と切返せる力、
そういった能力の総称したものがコーチアビリティだと。
そして、成長する個人や成果を出す組織は、
総じてこのコーチアビリティが高いということです。
言うなれば、
”コーチされる力(コーチアビリティ)”も重要だということです。
教える側だけでなく、教わる側のアビリティ(能力)の問題だと。
・・・なるほど、そうなんですよ。
教えたからには、しっかり反応し、
主体性を持って取組んでくれないと!
同書には、更にこのように書かれています。
以下、書籍『叱らない時代の指導術』(著:島沢優子)より引用抜粋
ただし、その力はコーチが育むものです。
選手任せでは育たない。
アスリートたちがそうなる環境を
まずはコーチがつくってあげなくてはいけません。
コーチアビリティを育める環境を用意していないのに、
コーチ側は自分の意見を述べることを選手に期待してしまう。
・・・イタタタ、です。
教わる側に主体性がないのであれば、
それは教える側にも責任があるのです。
水辺に連れていくだけで仕事を終えていませんんか。
その水の美味しさや、それを飲むことでどうなるか?
また、飲まなければどうなるか?を伝えていますでしょうか。
そして、伝わっていますでしょか。
もっとこんな水がいい!こんな飲み方は?という、
意見が交換できるような環境や関係性を創れているでしょうか。
そこまで含めて、コーチの仕事のようです。
組織的なコーチアビリティの強化に取り組んでいきましょう。
追記)
このコーチアビリティが適切に機能しているケースについては
下記もご参考ください(タイトルか画像をクリック)