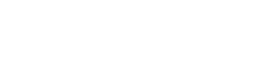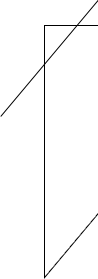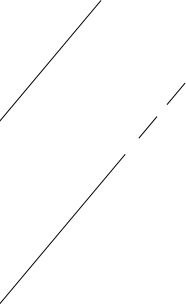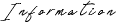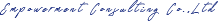弱さを前提とした性弱説的アプローチ
「水は低きに就く如し」というコトバがあります。

これは、孟子が性善説を説明するときに用いた言葉で、
人間の本性が善であることは、
水が高いところから低いところに流れることと同じような自然の摂理である
との意味だそうです。。。
そこから派生して、
「水は低きに流れ、人は易きに流れる」
という格言も生まれています(孟子がそういったわけではない)。
水の流れは普段意識しなくても、
後半の「人は易きに流れる」は、全くその通りと日々実感(反省)している方は、
僕を含めて多いのではないでしょうか?
人が弱い(易きに流れる)のも、自然の摂理なのかもしれません。
そんなことを考えていると、我が意を得たりという言葉がありました。
孟子の”性善説”ならぬ、”性弱説”です。
元キーエンス著者の書籍『キーエンス流 性弱説経営』(著:高杉 康成)にて
下記のように紹介されています(同書より引用、一部加筆修正)
「人は特別なこと以外は何でもできる」という前提に立つか、
「人は思っているよりもできないことが多い」という前提に立つか。
これが「性善説」の前提に立つか、「性弱説」の前提に立つかの違いになります。
性善説とは、人はみな本来善人であり、「正しく聞けば、正しいことを話してくれる」
「正しく指示すれば何でもできる」「常識的なことはみんな分かっている」というような考え方です。
一方の性弱説とは、人は本来弱い生き物なので、「難しいことや新しいことを積極的にはやりたがらない」
「目先の簡単な方法を選んでしまいがち」というような捉え方です。
多くの企業では、難しい仕事を任せるときも「できるだろう」と楽観視し、性善説でアプローチします。
一方のキーエンスでは、これを「できないかもしれない」という性弱説視点でアプローチします。
「任せた仕事をできる確率を高めるにはどうすればいいか」を優先して考えています。
この両者の差が、結果に大きな違いを生んでいるのです。
・・・なるほど。
”性弱説”、非常に納得感のある考え方です。
思ったとおりにならない(できない)理由を、
「悪い」からではなく「弱い」と考えることは非常に示唆に富んでいます。
なので、罰則や規則をガチガチに固めるのではなく、
「仕組み」を作ることが大事だ、と同書でも書かれています。
参考になると思いますので、課題感に共感される方は一読されてみてください。
僕たちは、残念ながら物事を都合良く期待してしまいます。
それこそ、性善説的に。
「人は易きに流れる」を日々自分の中で反省しているにも関わらず、
他人には、これくらいやってくれるだろう、と。
能力や可能性を低く見積りすぎる必要はありませんが、
弱さを内包していることを忘れてはいけないようです。
まずは、個人も組織も、
その”弱さ”を認め、”弱いという前提に立つ”ことが重要だと思われます。
その上での仕組みづくりを。
性弱説というアプローチを是非取り入れてみてください!
因みに”前提に立つ”は、ビジネスシーンにおいても重要なキーワードの一つです。
下記も参考にしてみてください(タイトルか画像をクリック)
特にセールスやマーケティングに携わる方は是非。

追記)
『僕のヒーローアカデミア』という漫画に、
通形ミリオというキャラがいるのですが、作中では結構な強キャラです。
しかし、その強さは、自分の弱さ(扱いづらい能力)に向き合い、
懸命な努力を続けてきからだ、という、少年漫画王道のシーンがあります。


漫画『僕のヒーローアカデミア』No.150 通形ミリオ より
ただ、大人になって思うのは、
穿った見方ですが、ではどうやってその努力を継続できたのか?です・・・
下記も参考にしてください(タイトルか画像をクリック)