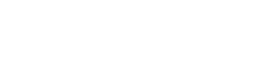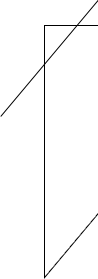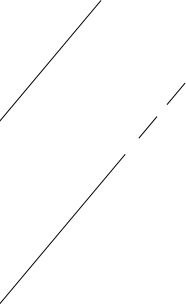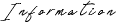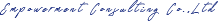三人寄って文殊の知恵をどう創る?
”三人寄れば文殊の知恵”という諺があります。
「凡人でも三人集まって相談すれば、すばらしい知恵が出るよ」という意味ですが、
はたして”文殊(もんじゅ)”とは何か?となります。
文殊とは、仏教の知恵を司る菩薩で、
正式には文殊師利菩薩(もんじゅしりぼさつ)というそうです。
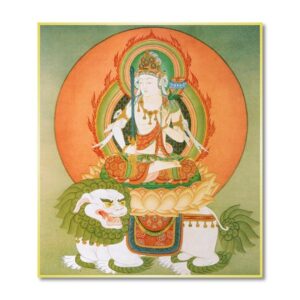
知恵を司どる菩薩様クラスのアイデアが出せるかは定かではありませんが、
どうやら集まって相談することは、統計的にも有益なようです。
所謂、集合知(集団的知性)と呼ばれるモノです。
わざわざ集まって、相談し、集合知を活かそうとするのは、
組織として良い意思決定をする為です。
では僕たちは、どのようにすれば、
この集合知による意識決定の質を上げられるのでしょうか?
『ソーシャル物理学』という書籍に、興味深い指摘がありましたので紹介します。
以下、書籍『ソーシャル物理学』(アレックス・ペントランド著)より引用抜粋・加筆修正
何が集団的知性の基礎となるのか?
これは予想外だったのだが、集団のパフォーマンスを上げると多くの人が信じている要素
(集団の団結力やモチベーション、満足度など)には、統計学的に有効な効果は認められなかった。
集団の知性を予測するのに最も役立つ要素は、
会話の参加者が平等に発言しているかどうかだったのである。
少数の人物が会話を支配しているグループは、
皆が発言しているグループよりも集団的知性が低かった。
皆さん、会議やミーティングを振り返ってみてください。
一方通行の伝達の場になっていたり、
一部の人だけが発言をしている状況になっていませんでしょうか?
意思決定の質を上げるには、
参加者各々がしっかりと発言することが重要なようです。
また、その意思決定が実行されなければなりません。
その点に関しては、同書に下記のように指摘をされています。
以下、書籍『ソーシャル物理学』(アレックス・ペントランド著)より引用抜粋・加筆修正
人々が共同作業を効率的に行うためには、ネットワーク制約と呼ばれるものが高い状態が必要になる。
これは集団に属するすべての人々の間で、繰り返し交流が生まれていることを意味する。
交流がリーダーとメンバーの間だけにしかない場合も、メンバー同士だけの場合も、
ミーティングのように「構成員が一堂に会して」しかない場合でもだめだ。
望ましいネットワーク制約の状態がどこまで具現化できるかは、
メンバーに対して、他のメンバーとも会話するかどうか尋ねてみることで検証できる。
答えが「ノー」」なら、彼らの間で会話が生まれるようにしなければならない。
私たちの研究によれば、協調的な行動を促す社会的圧力がどの程度存在するのかは、
直接的な交流の数によって計測することができる。
どうやら、集団で決定した選択を実行できる組織は、
普段からコミニケーションの頻度(メンバー間の交流)が高い組織ということです。
会議など特定の場だけでは、足りないようです・・・。
つまり、集団的知性の質が高く、すべからく実行に移せる組織は、
普段から皆が意見を出し合えている組織、ということです。
「なんだ、そんなことなら直ぐに取り組めるぞ!」という感じでしょうか。
それとも「いや、そこがなかなか難しくて・・・」の方でしょうか。
当たり前の話ですが、
普段から皆が意見を出し合える、ということは、
「意見を持っている」ということです。
僕は、ここが決定的に重要だと思います。
意見を持てるかどうか?の当事者意識の有無が大前提です。
まずは、そこから着手してみてはどうでしょうか。
それが現れるのが、会議での発言であり、日頃のコミュニケーションなのです。
そういった場を整えつつも、源泉となる各位の当事者意識。
ここに今一度、焦点を当ててみましょう。
併せて、下記もご参考ください(タイトルか画像をクリック)

追記)
因みに、集団的知性とは
「沢山人が集まれば、誰かが知っている」ということではありません。
三人寄れば文殊の知恵には、その要素も含まれていると思いますけどね。
その場合は、トランザクティブメモリーという概念が当てはまります。
詳しくは、下記もご参考下さい(タイトルか画像をクリック)